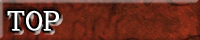


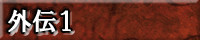
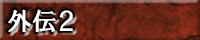
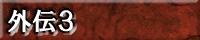
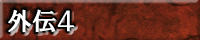
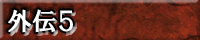
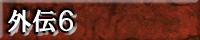
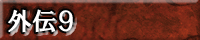
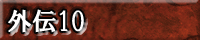





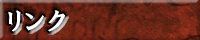

先史
勇者たち〈見張りの森〉の射手チャダ
チャダは、極めて寒い冬に生を受けました。その民は数週間の飢饉に苦しみぬき、チャダの母は子供たちを守ろうと必死でしたが、そのせいで母体は危険なまでに衰弱していました。チャダが無事世界の光を目にして数日後、母親はとうとう亡くなりました。村の老賢者は「この娘は祝福されている。この厳しい冬を生き延びたのだから」と予言しました。飢えと寒さによって、多くの人々の命が奪い去られてゆきました。それでも春は訪れ、村に希望と信頼が戻ってきました。 まだ幼い時分に、チャダは弓での狩りに習熟しました。村では、森の動物をナイフで殺めることは禁じられ、ただ弓矢を用いることのみが許されていました。この聖なる儀式によって狩られた獲物だけを、食することができたのです。チャダが最初の獲物を仕留めたのは、9歳のときです。こうした狩人の力によって、寒い冬の年月であっても、村は生き延びることができました。そしてほどなくチャダは、狩りだけにではなく、〈歌う樹〉に襲いかかる邪悪な怪物をくだすために、弓を取るようになりました。 北の魔術師エアラ
ハドリアは魔術の国です。その国境は、ハドリア海で隔てられています。そこで魔術は、世代を超えて受け継がれてきましたが、その能力は人によってまちまちです。エアラはといえば、傑出した才能の持ち主といってよいでしょう。極めて幼い頃、母親はその力の片鱗を目の当たりにしました。 エアラは草原に座りこみ、鳥の羽根で遊んでいました。羽根は宙に舞ったかと思うと、その手のなかに戻ったり、再び舞いあがったりを繰り返しました。両腕を大きく広げると、羽根はさらなる高みに到達しました。そして、とても彼女の小さな手では届くはずもない、遥か彼方にまで飛ばされました。ところがエアラは、やり遂げました。意志の力のみで、羽根を再び手中に引き戻したのです。 とはいえ、その才能が目に見えて開花するには時間が必要でした。気づくと彼女は、自分だけではなく、他人の力をも拡張するワザを習得していました。意志力で物事を改変できることに気づいた付近の人々は、彼女を手元に置いておきたがりました。そこでエアラは、偉大なる魔術の先達のように、自分の力を試す旅に出ざるをえなくなりました。そしてその旅こそが彼女を、宿命のアンドールへと導いたのです…… 〈深き鉱山〉のドワーフのクラム
クラムの母親はドワーフの女性で、盾ドワーフの鉱山の出でした。ブランドゥルに率いられた難民が〈廃墟の塔〉付近を通過する際、彼女はドラックを見初めました。ドラックもまた彼女を認めたため、ふたりは一緒にうまくやっていけると考え、行動を共にすることにしたのです。 アンドールに到着してすぐ、彼らは家族となりました。クラムは第七男で、勇敢なドワーフへと成長し、疲れを知らずに働き、恐れを知らずに戦いました。しかし逃亡奴隷と盾ドワーフの両方の血を引くという事実によって、クラムは微妙な立場におかれました。盾ドワーフたちと一緒に過ごしていても、居心地が悪いのです。父親の血統を、影で悪く言う者もいました。逆に彼の背景を羨む者もいました。それでも、怒髪天を突くほど怒っていても寡黙でいられる能力によって、彼はおおむね好かれていたのです。それは、ドワーフにしては稀有な才能なのです。 〈芦の国〉の戦士ソーン
王自身の古き友人より、ソーンは剣戟の技術を学びました。彼はこの村の近くに居をかまえ、平和で静かな余生を過ごしていました。野良仕事では、ソーンは父親の言うことを適当に聞き流しました。集中力がもたなくなると、スコップを正眼にかまえ、まるでそこに誰かがいるように振り下ろしました。それを、王の古き友人は見ていました。その流れるような打ちこみと、標的を捉える正確さに、舌を巻きました。既に戦闘で何をすべきかわかっている人間のような、見事な所作でした。そのすぐ後で、トロール戦争がアンドールの南方にまで発展したため、これは極めて幸運なことでした。たった14歳だったソーンは、無事家族の農園を守ることができたのです。 河畔の番人ケーラと水の精ファラ
ある日おそろしいことに、村が大火事に見舞われたの。みんな大きな桶で河の水を汲んだりして、ともかくあらゆる方法で、火を消そうとした。もちろんエトレもね。 水の精たちは、そんな人々の行動を観察していた。そしてファラは、そこにエトレの姿を見いだした。彼はひどい火傷を負っていたのに、その痛みも気にせず、水でいっぱいになった桶を何度も何度も村に運んだの。その甲斐むなしく、その夜、村は焼け落ちてしまったのだけど…… そんなエトレの勇敢さに、ファラは夢中になってしまったわ。愚かな恋心だった。まあ恋なんてたいていそんなものだけれど、ふつう水の精なら抱くはずもないその感情に身をまかせ、彼女は河を離れたの。人間を遠巻きに見守るという精霊としての生きかたを捨てて、自分の心に従ったのよ。 その熱いまなざしに、エトレは困惑するしかなかった。精霊であるファラには、はっきりした輪郭もない。美しかったけれど、恐ろしくもあった。ファラはしばらくエトレのそばに留まり、なにくれとなく甲斐甲斐しく手助けをしたわ。でもすぐにその想いが、永遠の片思いでしかないことを思い知らされたの。エトレには妻がいた。ファラは苦悩し、すべてを忘れようと、仲間のいる河へ戻ろうとした。でも水の精たちは彼女のわがままな行動に対して罰を下し、受け容れを拒んだ。ファラは二度と故郷に戻ることは許されず、追放されてしまったの。 少し経って、しかたなくファラはもう一度エトレの元へと向かった。悲嘆にくれるファラに心を打たれ、同情したエトレは、これからずっとそばにいて人々のために尽くしてはどうかと勧めた。ファラはそれを受け容れ、その日からずっとその務めを果たしてきたの。こうしてエトレは初代・河畔の番人となり、子々孫々子孫・今に至るまで、一族はその責務を受け継いでいるのよ」 ケーラは息子のヤニスを見つめました。彼は水の精ファラを悲しげに見つめていました。 「あのひとは、絶対に河に戻ることはできないの?」 「ええ、できないわ。かつてエトレに抱いていた想いは、今や大きな苦悩となってしまった。彼女は本当に孤独になってしまった。それなのに私たち河畔の番人の一族を何百年も助けてくれている。お母さんはそのことを、本当にありがたいと思っているわ。いつかあなたも河畔の番人としての務めを受け継ぎ、ファラは忠実な同行者となるでしょう。エトレはただの農夫でしかなかったけれど、その遺産として、彼女は私たちと共にありつづけるのよ」 その水の精はゆっくりと近づき、ヤニスの手にそっと触れました。そこへ夏の露から生まれたやわらかな風が吹くと、彼女の姿はどこかへ消えてしまいました。 怪物たち竜タロクとその眷属
トロール
アンドールの人々黒魔道士ファルクル
魔女レカ
盗賊ケン=ドル
酔いどれトロール亭
伝説の四つの盾星の盾
絆の盾
嵐の盾
外の世界に対する彼の探求心は、送り出した調査隊によってもたらされる報告によって、かろうじて堰き止められていました。こうして彼は、〈歌う樹〉の守り人や、奴隷使いの国から逃げのびて今やリートラントの住人となったアンドールの人々のことを知りました。それまで盾ドワーフの富を増すことにのみ執着していたハッルヴォルトにとって、目から鱗の情報でした。以後のリートラントの人々との通商をかんがみて、〈市橋〉の建設を命じました。 それでも彼の好奇心は止まるところを知りません。ついに“洞窟”を出て、まずはアンドールを、その次にはハドリア海を探検する決意をしたというわけです。その決意に至るまでの直接の動機もしくはきっかけが何だったのかは、今に伝えられていません。ひょっとすると、さすらいの商人からでも伝え聞いたのかもしれません。ともかくハッルヴォルトはある日いきなり、狭霧諸島、タル族、ハドリアの魔術師、海上の城塞、そして炎の剣について語り始めたというのです。 盾ドワーフの掟にそむくとは分かっていましたが、ハッルヴォルトは意に介しませんでした。不在時の統治は、息子ハッルガルドの手に委ねました。このこともまた、臣民の怒りを買いました。ハッルガルドは父親にも増して衝動的な性格であり、おまけに齢80にも満たず、みなが跪くにはあまりにも若すぎたのです。 さて話を戻しましょう。出発の前日の朝、ハッルヴォルトは武器庫に赴きました。きめ細やかに編まれた鎖帷子を着込み、その上から黄金の胸当てを装着し、ごつい大兜をかぶったとき、武器庫の隅に置かれた1枚の盾に目が行きました。拾い上げ、豪華な装飾を観察するうち、かつて鍛造術を極めて4つの力の盾を作りあげた竜ネハルと盾ドワーフの職長クレアトクのことが脳裏に浮かびました。そして手にした銀の盾を眺めながら、笑い声を上げたのです。 「これは〈役立たずの盾〉ではないか! あっはっはっは!」 事実この盾は、すべてのドワーフにとって失望の代名詞でした。かつてネハルとクレアトクは、4つのうち最も優れていると称される〈星の盾〉を作り上げました。どんな絶望的な状況をも跳ね除け、運命を好転させる力を秘めた盾です。その後すぐ、それに勝るとも劣らない〈絆の盾〉が鍛造されました。装備する者は他のドワーフから力を授けてもらったり、逆に自分の力を分け与えたりできる盾です。これによってドワーフたちは離れた場所に居ながらにして、互いを守りあうことができたのです。 この驚嘆すべき2枚の盾の後で、盾ドワーフたちの期待は大いに膨らみました。ネハルの灼熱の炉と、クレアトクの鉄床から生み出される次の盾は、どんなものなのか? いかなる守護の力が秘められているのだろう? こうして極上の金銀が次々と運び込まれ、間もなく新たな盾が完成しました。 その盾は軽く、精緻に装飾されていました。初めて披露されたとき、大広間のたいまつの火によって、それは銀色に煌めきました。ところが注意深く調べてみても、その盾からは特別な力など一切見出すことはできなかったのです。多くのドワーフが「もうクレアトクとネハルは、鍛造の魔力を失ってしまったのではないか」と危惧しました。 二者は続いて4枚目の盾を完成させ、その心配は杞憂であったことが証明されました。その能力は、3枚目の疑惑を払拭するに足るものだったのです。その最後の盾に関しては、後にドワーフと竜との間に戦争をもたらす引き金となった可能性が指摘されていますが、その真相は今となっては闇の中です。 いずれにせよドワーフたちはクレアトクとネハルの手腕を讃え、何の力も見いだせなかった例の盾については取るに足らない失敗作として忘れることにしました。たまに思い起こす者がいると、単に〈銀の盾〉、もしくは〈沈黙の盾〉、そしてほとんどの場合〈役立たずの盾〉と呼ばれました。 意外に思われるかもしれませんが、4枚のなかで最も長く“洞窟”の領主の管理下に置かれたものこそ、役立たずの銀の盾だったのです。というのも他の3枚は、竜や怪物との戦争のさなかに失われていったからです。 ハッルヴォルトは、精巧な銀細工の表面をさすりました。 「役立たずの領主に、〈役立たずの盾〉か。お似合いだわ」 それで笑わずにはいられなかったのでしょう。彼は顔にいたずらな笑みを浮かべながら、その盾と共に武器庫を後にしました。
ハッルヴォルト侯爵は、人生で初めて船矢倉に登り、顔に吹き付ける潮風を楽しみました。グルトもまた、見事な景色と、眼下に広がる海面を目にして大いに喜びました。いっぽうラダンと2人の従者は船酔いに苦しみ、ほとんどを船室で過ごしていました。 3日目、状況が一変しました。大きな衝撃が船を襲い、ラダンはベッドから転げ落ちました。なんとか立ち上がると、甲板のほうから怒号が聞こえてきます。すぐに現場に向かうと、船乗りたちはてんやわんやの大騒ぎです。荒れた海上の高い波間から、鋭く突き出た岩礁が見えました。ドル船長は、強風に負けじと大声で、進路を変えるよう操舵手に命じました。 ハッルヴォルトとグルトは船の船首側におり、甲板から海に投げ出されないよう、力いっぱいしがみついていました。やがて船は、衝突寸前で何とか向きを変えることができたようです。岩礁は右舷はるか後方へと去り、ラダンは安堵のため息をつきました。しかしその直後、今度は船のすぐ前方、今まで何もなかったところに新たな障害物が出現しました。 「気を付けろ、また岩礁だ!」 ラダンは叫びました。 ところがドル船長は、首を横に振りました。 「岩礁なんかじゃねえ」 「なんだと?」 ラダンは、目の前に現れたものを、まじまじと確認しました。岩はどんどん大きくなり、水中からぬっとそびえ立ったのです。 「ありゃあ、アログだ! 砲手、バリスタ用意!」 船長が叫びました。 何が起こっているのかラダンが理解するより早く、また別の岩が浮上してきました。そしてその岩の表面に、黄色く光る双眸が現れました。ラダンはこのような生き物を、いまだかつて見たことがありませんでした。ごつごつした石に覆われた皮膚には、貝や海藻がこびりついていました。 その巨大な石の爪による一撃はフォアマストをへし折り、船矢倉の半分までもがもぎ取られました。しぶきをかぶりながら、船は横転しかけました。一瞬の後、船の傾きが戻ったとき、船員の1人が、まるで目に見えない紐にでも引っ張られているかのように宙を舞いました。そして黄色い牙がびっしり生えたアログの黒々とした口の中へと、吸い込まれていきました。さらに1体のアログが、左舷に浮かび上がります。ラダンの背後で、船尾バリスタの起動音がし、鋼鉄の巨大な矢がうなりを上げて頭上を飛び越えました。惜しくも、怪物には当たり損ねました。その怪物もまた腕を振り上げ、船にさらなる一撃を加えました。弾け飛ぶ木材。この混乱のさなか、ハッルヴォルトは片手で綱を掴み、まだ持ちこたえています。もう一方の腕には何かを装着しているようでしたが、最初はよく見えませんでした。それは、あの〈銀の盾〉だったのです。一天にわかに掻き曇ったかと思うと、高く掲げられた〈銀の盾〉から、闇夜に輝く一点の綺羅星のごとく、まばゆい光が放たれました。一陣の風が吹き、覆いかぶさらんばかりの大波が、アログどもの石の顔を打ち据えました。 かろうじて無事だったもう1つの帆が、はちきれんばかりに風をはらみ、船は押し出されるように前進を始めました。そのすさまじい推力に足をすくわれ、ラダンは転倒しました。アログの咆哮が聞こえ、すぐ立ち上がろうとしましたが、むなしい努力でした。しだいに怪物たちの咆哮は遠ざかり、やがて艤装のきしみ、風のうなり声、そして船首が大波に叩き付けられる音以外、何も聞こえなくなりました。
突如、身の毛もよだつ絶叫が、その会話を遮りました。ふたりが飛び出すと、ハッルヴォルト侯爵がふらふらと船室から出てくるところです。両手で喉元の傷を押さえ、噴き出す血を止めようとしていました。続いてドル船長が出てきました。片手に血まみれの短剣、もう一方の手には今や〈嵐の盾〉の名で船上の全員に知れ渡ったあの銀色の盾を掲げていたのです。彼は、動揺で顔を見合わせている部下たちのそばを素早くすり抜け、積載されている樽のひとつに飛び乗りました。 「諸君、今日という日を忘れるな! 俺たち全員が富を得た、今日という日を!」 船員たちは、ひそひそと言葉を交わしました。その多くの者は、そのとき初めて、喉をぜいぜい言わせて苦しむドワーフの領主に気付きました。 「諸君、この盾は俺たちが報酬として頂戴した!」とドルは叫びました。「このチビどもは、俺たちを金貨なんぞであしらおうとしたようだが、見ろ、俺はお前らのために〈嵐の盾〉を手に入れてやったぞ!」 ラダンが背負っていた斧を手に取り、背後にいた深層よりのドワーフに目配せをすると、彼らもおのおの武器を構えました。グルトはといえば、負傷した従兄に駆け寄り、庇うように覆いかぶさりました。 ヤリ=ドルは、ラダンに向かって居丈高に続けます。 「ドワーフども、お前らも侯爵のように死にたくなけりゃ、今すぐ俺の船を降りるんだな。多勢に無勢ってもんだ」 雷鳴が轟き、ヤリ=ドルは自分の声が届くようにと、叫びました。 「陸まで泳ぎきるか、その途中でくたばるか、二つに一つだ、ドワーフどもが!」 その言葉と共に、盾が天高く掲げられると、ラダンはその力の解放にそなえて身構えました。ところがこのときは、盾自体から輝きが発せられることはありませんでした。代わりに、別の強烈な閃光が走りました。頭上の積乱雲より、盾の上に稲妻が降り注いだのです。ヤリ=ドルの体は爆発に見舞われたかのごとく宙を舞い、船員たちの足元に叩き付けられました。痙攣するその体は、真っ黒に焼け焦げていました。 そんな船長と、その隣に無傷で転がる盾を目の当たりにして、船乗りたちは身動きひとつできませんでした。ただへの字に白鬚をたくわえた船乗りだけが言い放ちました。 「死んじまった」 すると別の船員が船長の死体の脇を通り過ぎ、グルトとハッルヴォルトのそばへ駆け寄ったかと思うと、自分の服を引き裂いて縞模様の布きれを差し出しました。グルトはそれで領主の傷を押さえました。また別の船員が、盾を拾い上げてラダンに渡しました。 これがドル船長の最期でした。そして悲しいことに、侯爵も助かりませんでした。グルトが止血を諦めたとき、ハッルヴォルトは笑いかけ、自分をこの北方の地に埋葬するようにと命じました。潮風をこよなく愛したハッルヴォルトでしたから、これ以上の冥福が望める場所はなかったことでしょう。間もなく侯爵が亡くなると、ドワーフたちは島に上陸し、海岸からそう遠くないところに彼を埋葬し、そこを最初の野営地としました。探索隊の指揮はグルトが引き継ぎました。一方、ラダンは船に残りました。ハッルヴォルトと〈嵐の盾〉について報告すべく、帰途に就かなければならなかったからです。彼は船乗りたちをずっと信用していませんでしたが、それでも誰かが“洞窟”まで戻らなくてはなりません。再び南の大地を踏むまで、ラダンは一瞬たりとも眠らず、斧を手放しませんでした。〈嵐の盾〉は、北方に留まるグルトの元に残しました。 およそ一月後、ラダンは無事“洞窟”まで到着しました。目立った怪我こそなかったものの「人間に対する根深い不信感」という大きな心の傷を負っていました。この心の傷が癒えるには、相当な時間を要しました。そしてラダンからの報告を耳にしたハッルガルドにも、この人間不信は伝染してしまうのです。その一方、ほかの多くの盾ドワーフたちの心の中には、かつてハッルヴォルト侯爵が抱いたのと同じ憧憬が芽生えていました。後に出発の機運が盛りあがると、ハッルヴォルトを手本とする多くの盾ドワーフたちが、“洞窟”から旅立って行くことになるのです。 その間グルトは坑道を掘り進め、銅や金のみならず、とりわけ多くの銀を産出する豊かな鉱床を発見しました。“洞窟”からやって来た盾ドワーフの仲間が加勢したこともあり、北方のドワーフ国家の拠点として〈白銀の城窟〉が築かれました。彼らはやがて“銀ドワーフ”と呼ばれるようになりますが、それが発見した銀の鉱脈を意味するのか、〈嵐の盾〉の元の名から取られたのかは、はっきりしていません。そしてその〈嵐の盾〉が今でもその地に残されているか否かは、《北方への旅立ち》の伝説に挑んだ勇者のみが知ることとなるのです。 〈竜の遺産〉の時代
ハドリアの二つの魔術結社
ユラの魔術は本来、物質や生物の根源にある力を、増大したり制御したりするものでした。ところがある日、そのやりかたに飽き足らない者たちが、さらなる知識を求めてユラの同胞と袂を分かちました。彼らは、事物に自らの意志を押しつけて改変したり、もともと存在しないものを生み出したりする魔術の研究を始めました。こうして黒魔術が見いだされたのです。 道を外れた魔術師のなかでも、最強と呼ばれたのがオルヴァインでした。その心のなかは、この地を厳冬の苦難から解き放ち、“わだつみ”を抑圧しようとする意志に満たされていました。暴風侯アークテロン、呪操姫ケンフィラー、深淵公オクトハンを屈服させねばならぬ、と。 同志とともに黒魔術の研究を進めて数年、ある夜オルヴァインは暗闇の中、猫背で書物に向かいながら、とある計画を思いつきました。 そうだ、魔法の武具を鍛え上げよう。それさえあれば、単独で“わだつみ”に対抗し、打倒しうる。とはいえ、あの恐るべき“わだつみ”に立ち向かうなどという無謀な試みを、いったい誰が引き受けるというのでしょう? オルヴァイン自身は、知識欲こそ旺盛ではありましたが、百戦錬磨の武人からは程遠い人物でした。 ところが運命は、彼に微笑んだのです。ことの始まりは、ハドリアのとある海岸に、一隻の大型船が到着したことでした。それは誇り高き海王ファラタンが船長を務めるタンブル号で、ちょっとした騒ぎになりました。小麦やライ麦のほかにも、ワイン樽、嵐の谷のゴートチーズ、そして後にアンドールと呼ばれる遥か遠き竜の国からの椰子の実やキノコといった珍しい食料品が、たくさん積載されていたからです。 その報せを耳にしたオルヴァインは、この引き合わせに感謝しました。海王の名の意味は“炎の子”。彼の計画に最適な人材ではないでしょうか? いざ海王を出迎えてみて、オルヴァインの見込みは、確信に変わりました。ファラタンは、船旅における数々の危機をいかに乗り越えたのかについて、嬉々として語りました。そして最後に、冬の終わりをどれだけ強く願っているか、という話でしめました。共に食事をし、熱燗の蜂蜜酒を飲み交わした後、オルヴァインは自身の計画を海王に打ち明けました。“わだつみ”を打倒し、冬を永遠に放逐しようと。そして話が創り出そうとしている魔法の武具にまでおよぶと、ファラタンの瞳が輝きを増しました。その夜、ハドリアの命運は一変したのです。 オルヴァインとその同志は鍛冶場にこもり、暗黒の力を用いて、魔法の武具を鍛えはじめました。その間、災厄に満ちた灰色の煙が忍び寄り、炎の上で蠢いていました。 最初に鍛え上げられたのは炎上剣ファルリオンです。いざ鞘から抜かれると刃から炎を噴きだす、ずっしり重たい両手剣でした。オルヴァインの剛鉄槌は、その名の通りオルヴァイン自身が鍛えた作品で、装備する者は戦うたびに力を増すのです。そして最後に海王を“わだつみ”の脅威から守るべく、ファラタンの力兜が創られました。 完成の報を受け取った海王はすぐにクリッペンヴァハトに戻り、優秀な船乗りを集めて艦隊の編成を始めると同時に、狭霧諸島の各島へ人員を配置しました。 海王がハドリアに到着すると、オルヴァインは魔法の武具を引き渡し、艦隊の出航を誇らしげに見送りましたが、ファラタンはこのままハドリアを見捨てて行ってしまうのではないか、という一片の不安は拭えませんでした。 それから海王は、長きにわたって行方知れずとなりました。オルヴァインには、気を揉みながら待つことしかできません。その間にも、彼はより深く黒魔術の研究に没頭しましたが、知れば知るほど、ある疑念が強まっていきました。黒魔術とは、より大きな代償を要求するものではないのか? 直感は、そう告げていたのです。 数か月が過ぎ、苛烈な暴風がハドリアを吹き抜けました。轟く嵐のさなか、海上を漂流するファラタンが発見されました。艦隊は“わだつみ”との戦闘で壊滅し、さらなる報復として、城塞クリッペンヴァハトまでもが破壊し尽くされたというのです。そして次は、ハドリア本島の番です。 怒り心頭の海王は、オルヴァインに“わだつみ”どもへの反撃の手立てを求め、アークテロン、ケンフィラー、オクトハンをなんとしても駆逐せよ、と命じました。こともあろうにオルヴァインは、それを拒みました。今や黒魔術がもたらす災禍の全貌を、目の当たりにしていたからです。黒魔術とは常に、それがもたらす恩恵以上の破滅を、もたらすものだったのです。 こうしてオルヴァインは、魔法の武具のみならず、自らが得た黒魔術の知識を封印すべく、鉄の塔の建造を指示しました。塔が完成した暁には、かつての同志に、共に鉄の塔に籠るよう勧めました。それもすべてはハドリアの人々を守るため。怒り狂う“わだつみ”を鎮めるには、そうするしかなかったのです。こうしてオルヴァインは、海王ファラタンのみならず、自分に従わない者すべての敵となりました。世界から暗黒の知識を消し去るためには、みずからの手を汚し、かつての同志を討つことすらためらいませんでした。彼の理性は、“わだつみ”の呪いによって崩壊していたのです。 オルヴァインは、最年少の魔術師たちに封印をまかせました。同志を先に送り、最後の者として塔に入るその瞬間、オルヴァインはたどたどしい口調で、ハドリアの終焉を予言しました。魔術師たちのあいだに不和が生じた際、結束を誓わなければ、ハドリアは滅ぶであろうと。その背後で塔の扉は閉ざされ、すべての黒魔術は封印されました。オルヴァインとその同志たちが姿を見せることは、二度とありませんでした。 その犠牲は少なからぬ効果を上げました。嵐は収まり、“わだつみ”どもは怒りを鎮めて深海へと戻って行きました。ただ、冬の寒さだけは後に残りました。 取り残された、若いながらもそれなりの教育を受けていた魔術師は、以降“鉄の塔の魔術師”を名乗りました。 海王ファラタンはハドリアに留まり、残った魔術師から教えてもらえる限りのことを学びました。王としての尊厳などは既に地に投げ捨てていましたが、“わだつみ”の力に服従し、ハドリアと周囲の海が永遠の冬に覆われることを容認したオルヴァインのことは、たいそう腹立たしく思っていました。 それから彼はハドリアの首都ノルドガルドへと移り住み、同様の不満を抱く魔術師がいないか探してまわりました。そしてついに、オルヴァインの目を免れて黒魔術を受け継ぐ魔術師たちが、少数ながら隠れ住んでいることをつきとめたのです。 そんなさなか、ファラタンはひとりのハドリア女性と巡り合い、“炎の海”という意味の息子ファルクマルもうけました。ファルクマルは力を求め、鉄の塔に封印されし知識への渇望を抱きながら成長しました。 父ファラタンが没する頃、ファルクマルは既に知りうる限りの魔術を会得していました。それでも知識への渇望は止むことはなく、数年後、ついには新たな魔術結社である“炎の魔術師団”を設立したのです。永遠の冬による支配を不服とする彼らは、“鉄の塔の魔術師団”に対して、保有する知識を解放するよう、何年にもわたって要求し続けました。 幾度もの長き冬を越えて、塔と炎というふたつの魔術結社の対立は、強まるばかりでした。その間には黒魔術の影が横たわり、ファルクマルは互いの憎しみを煽りました。彼の力は最高潮に達していましたが、それでも無理やり鉄の塔を占拠したり、闇の知識を解放させたりするほどではありませんでした。 そんな折、彼にもひとり息子が生まれました。誕生の夜、〈永劫の炎〉がまばゆく輝いていましたが、同時にハドリアは強烈な嵐に見舞われていました。瞳に魔法の炎のゆらめきを秘め、絶大なる力を予感させる息子を、ファルクマルは誇らしげに見つめていました。その子こそ、ファラタンの遺志を継ぎ、みずからも成し得なかったことを成し遂げるようにと、願いをかけました。黒魔術を封印より解き放ち、憎き“鉄の塔の魔術師”たちを打ち負かして、焼き払わんことを。 その子に授けられた名は、“炎の死”ファルクル。その経歴は、また別の物語で語られることになります…… 海王ファラタンの怨念
王は、“わだつみ”のうち1体への勝利を(それが偽りであるとも知らず)大いに祝いました。生き残った者たちは称えられ、命を落とした者たちは弔われました。人々は大いに飲みかつ食らいました。それは長く記憶に残る宴となりました。 時は流れ、再びケンフィラーとその操舵士の道は交わりました。その名はキャレム。今やファラタン配下の船長となり、後にクリッペンヴァハトと呼ばれることになる都市ファラタニアンと、海王ファラタンの居城ヴェルフトハイムとの間を往き来していました。 とある航海の最中、どういうわけかキャレムの船は航路を外れ、荒海に投げ出されました。そこにケンフィラーが現れ、かつて見初めた操舵士を、その呪縛へと取り込んだのです…… その船と乗員はみな行方知れずとなり、死んだものとして丁重に追悼されました。キャレム船長は名うての海兵でもあり、その死は王にとっても大きな痛手でした。 「“わだつみ”どもを支配できないものか」と王が悩み始めたのは、その頃のことでした。すぐに北方へと船を向け、魔術師の地たるハドリアで当時最も力があったオルヴァインに、魔法の武具の製作を依頼しました。 そんなある日、黒きコグ船の噂が広まりました。その船は、突如として虚空より現れ、忽然と姿を消すというのです! 数々の商船が襲われ、積み荷を奪われました。この黒きコグ船には通常の船員や兵士だけではなく、不可解なことに……魔女、魔法使い、ドルイドといった力を秘めた存在も乗り組んでいました。いたるところで目撃されていたにも関わらず、誰もその黒きコグ船に近づくことは、長いこと叶いませんでした。 死んだと思われるようになると、キャレムは自分の船を破壊しました。ケンフィラーは彼に、それまでよりも大きく強力な代わりの船を贈っていました。キャレムは自らの手で、かつての乗員の大半を殺害しました。巨大な猛禽ロアは、剣のように鋭い爪と赤く輝く翼で、その虐殺の手助けをしました。キャレムの初めての船乗り仲間であったペローと、ファラタニアンに連れて行かれるはずだった背の曲がった老人クルムだけが、生き残りました。 老練なるクルムは「自分は魔法使いである」と話し、その証明として、船を丸ごと濃霧で覆い尽くす不思議な薬を生成してみせました。それを見たキャレムは「クルムは役に立つ」と判断しました。またキャレムはとある船室で、怯えた目をした青い肌の少女を見つけました。ケンフィラーからの贈り物で、その娘ケンタールでした。船は彼女の新たな住処となりました。彼らは海へと繰り出し、略奪行を繰り返して、徐々に乗員を増やしていきました。嵐の谷への襲撃では、タル族のドルイドであるトッガーを引き入れました。彼の作る秘薬は、配下の全軍勢へ、より強大な戦闘力と水中呼吸の能力を付与しました。 別の襲撃においては、ハドリアの女学生エアン・クヴェラを捕獲しました。魔術師養成の旅を終えようとしていた彼女は、長らくキャレムの影響力に抗っていたものの、ついにケンフィラーの娘ケンタールによって精神を侵食され、キャレム船長の下でその能力を発揮するようになりました。 こうしてキャレムは北海の覇者への道を歩み、その力は確固たるものへとなっていきました。その脅威が表面化してきたことで、王ファラタンは“わだつみ”との戦いを中断し、黒きコグ船の捜索を始めました。 その忌々しい船を見つけだし、追い詰めるために、王の保有する全艦隊が投入されました。黒きコグ船は、風力によるものだけではない不気味なまでの速さで、西方へと逃亡しました。王ファラタンと彼の艦隊が追跡を開始すると、やがて前方に、見たこともない海岸が現れました。《狭霧諸島》の島のひとつでしたが、王はそれまで、その存在を知りませんでした。略奪の拠点となっている秘密基地に違いありません。その岸辺で、黒きコグ船は灰色の帆を畳み、素早く海面にボートが下ろされ、その乗員たちは逃げるように上陸を開始しました。王はすぐさま追撃を命じ、配下の海兵たちは、逃げ遅れた敵を皆殺しにしました。 眼前には、険しい山々がそびえ立っていました。島の奥へと進み、ようやく最初の峰を超えたとき、王は息を呑みました。山脈の向こう側に、暗く不気味な森が広がっていたからです。彼方よりの腐敗臭が、鼻を突きました。漆黒のトカゲのような生物が、岩棚から続々と這い出して来ました。一部はゴルであり、一部はもっと恐ろしいものでした。ともかくそこは悪しき場所であり、致命的な罠でした。足を踏み入れてはいけない領域だったのです。王はこの島をナルコン(海兵の言葉で、罠や待ち伏せのこと)と名付け、退却を命じました。ところが号令を聞き逃し、深追いする者もいたのです。撤退する兵たちをしり目に、敵を追撃する者のなかには、ファラタンの旧友ルーフの姿もありました。 (致しかたあるまい、あやつを助けるのはもう無理だ) 北海の支配者としては、少数を助けるために、多数を危険にさらすわけにはいきませんでした。海王ファラタンは、その山脈より北方に対して大きく腕を広げ、呪いをかけました。 「怪物や反逆者が、二度とこの島を出ることなく、永遠に苦痛と欠乏に苦しみ続けるように」 こうしてこのナルコンという島を呪った王は、配下と共にその地を去ったのです。 その声が聞こえる場所に潜んでいたキャレムは、不意に自分の精神と肉体の変容に驚愕しました。彼のなかを、恐怖と怒りが駆け抜けました。気付くと、光る霊体が自分の肩に手を置いていました。その瞬間、海や船に関する記憶は失われ、この島と関連のないあらゆる記憶は、忘却の黒い影に置き換えられてしまいました。この島から抜け出すには、ここではないどこか別の場所についての知識や、その存在を信じる希望の心がなければなりませんでしたが、それはこの呪いによって永久に奪われてしまいました。 百年を超える歳月が流れました。魔法の武具は完成しましたが、そのあまりの強大で危険な力のために封印されました。ファラタンは世を去り、その血統を継ぐファルクルという名の若き魔術師が、大いなる災厄をもたらすために、この世に生を受けました。南方クラードより、ひとりの奴隷が逃げ出し、かつて竜の国だった場所にアンドールを築きました。そこで活躍した勇者たちは伝説となり、そのうち2人が、呪われた島ナルコンで遭難しました。 チャダとソーン。彼らはそこで、キャレムや黒きコグ船の呪われし軍勢に出くわすのでしょうか? 彼らはファラタンの呪いを振り切り、その島から抜け出すことができるのでしょうか? ヴィンターブルク城
かつて灰色山脈には、単なる地下通路や広間に留まらないドワーフの一大帝国があった。岩から削り出し、不気味な塔や要塞を築きあげた。自然石の眺めと調和するよう、最新の注意を払われ、まるで石造りのこだまだった。竜やドワーフの巨大な彫像が設置され、物言わぬ見張りのように霧の上に突き出していた。 最も美しく大きな砦は、カルルツァールと呼ばれていた。遥かなる峰に建てられていたため、夏であっても、鐘楼はしばしば積雪に覆われていた。したがってすぐに、ヴィンターブルクすなわち〈冬の城〉という二つ名で呼ばれるようになった。 長い歴史のなかで、その主は何度も変わった。最初はもちろんドワーフである。竜や巨人との戦争のなかで、彼らは地下へと撤退し、この不可思議な砦は放棄された。 すぐに竜たちが、その広い塔や大広間を棲み処とした。だがそれも短い間だった。巨人族が砦に目を向けたからだ。美しく強い砦に。彼らはドワーフではなかったが。ドワーフの細工の技と製品の質には一目置いていた。 けれどヴィンターブルクに興味を持った第一の理由は、その場に残った竜のような敵が、隣接する国境にいることだった。当時の竜どもは賢く強力で、巨人たちを遥かに凌駕していた。危険な隣人だった。 けれど唯一巨人たちの中で、竜に恐れられた存在がいた。その呪術師は、みずからをノミオンと称していた。魔術を探求し、他者を支配する力を得た最初の巨人だ。その力は急速に増大し、飲めば巨人戦士の意志力を増す薬の調合に成功した。さらに改良を続け、それによって他者の意志に介入し、支配できるようになった。巨人の死骸を骨の剣士として復活させることができるようになると、彼らの生活は一変した。そして自分たちのことをクラード、すなわち〈不死者〉と呼ぶようになった。とはいえ他の種族同様、時がくれば命は尽きるのだから、不適切極まりない名称であった。蘇った死者どもは、忠実にノミオンに仕えた。この死霊術によって、ノミオンは他の巨人とは異なる存在となり、また実際に不死となったのだという。 ノミオンはこの知識の伝承を許した。弟子たちは神殿を築き、悪しき魔力を空気に乗せて広めるべく〈黒き樹〉を植え、滋養を与えた。 ノミオンは、それだけでは満足しなかった。灰色山脈にあった廃棄されたドワーフの塔を捜索し、長い時間をかけて南方世界で最も強力な生物をつきとめた。そしてその精神を呪縛し、奉仕させることに成功したのだ。 そしてすぐさま、ヴィンターブルクへと襲撃をかけた。この恐るべき奇襲によって、多くの若き竜が命を落とした。往年の誇り高き砦は、不可解極まりない生物の打撃によって崩壊した。 その日の終わりに、ノミオン自身が到来した。すると間もなく、あらゆる竜の中で最も強く最もずる賢いタロクは、この呪術師が、あの生物を陰から操っていることを知った。ノミオン自身は戦闘など不得手であり、あの強力なしもべはヴィンターブルクで他の竜たちとの戦いに忙しかった。タロクにとってノミオンを滅ぼすことなどは造作もなく、一瞬で灰の山となった。 後に原トロールと呼ばれるこの生物は、やがてヴィンターブルクを離れ、深い眠りへと戻っていった。ヴィンターブルクの虐殺を生き延びた竜はほとんどおらず、砦もまた破壊されたのである。? わずかに残った竜たちは、単なる岩と化して防衛の役に立たなくなったヴィンターブルクを離れた。その廃墟に何者かが忍びこんだのは、間もなくのことだった。かつてノミオンであった暗色の灰が、しめやかに侵入した。碧い光とともに、青白い人影が起き上がった。それから長い間、その影は灰色山脈の廃棄された砦や塔の間をさまよっていた。ノミオンの怨霊であった。 この秋、諸君が灰色山脈を抜ける頃に、この亡霊はまだそこにいるのであろうか……? 異邦よりの贈り物
ウンダヴァール王子は夕空を眺めていた。曇っていて薄暗い。まるでクラードの大要塞ボルクホルンを覆う、鉛の層のようだ。ウンダヴァールの全身は虚無感に蝕まれ、どうにも起きる気がしない。塔の自室の中央にある石の寝台に、灰色の巨体を横たえている。辺りには、汚物と腐った食品のひどい臭気が満ちていた。 不意に、いくつか悲鳴が上がったようだ。曇った心のせいで、それが本当に叫び声だと認識するまで時間がかかった。中庭だろうか? それでも興奮は湧き上がってこない。遥か昔に置いてきてしまい、その感覚を思い出せない。だが心臓は勝手に早鐘を打つ。不承不承、起き上がった。ふと、脱走騒ぎではないかと思い当たった。滅多にあることではない。どうして自分だけは逃げおおせると思えるのか? そんなもの、おとぎ話にすぎない。逃げようとするものは少なく、成功する者はいない。ほぼ不可能だ。何十年か前、小規模な奴隷の集団が逃げ出したきりだ。そのとき自分の家系に刺さった屈辱のトゲは、いまも抜けず深く刺さったままだった。逃亡など、二度と許してはならない! 王子は、刻印のある石階段を踏みしめ、ゆっくり塔を下りていった。左翼から聞こえる絶叫はより大きくなり、自然に歩みが速まった。途中、骸骨剣士の衛兵どもに、しげしげと観察された。「クソッ」もう完全に目は覚めていた。「どうせ俺は肥満の出来損ないさ。骨どもときたら、この俺に残った最後の矜持さえ奪い去ってしまう!」召し使いを呼び戻そうと、肺に大きく息を吸いこんだ瞬間、骸骨剣士の目に激しい光が宿った。直後、カタカタと骨を鳴らし、手にした槍を宙に泳がせる。この警告に、ウンダヴァールは足を止めた。ここで何が起きているというのか? 疫病? 反乱? そこで、うっかり愛剣も鎧も身に着けずに出てきてしまったことを悔やんだ。逃げ出した奴隷なら、素手でも締め上げることが。だが、これは何だというのか……虚空に塵の雲があり、その向こうを見通すことができない。 いきなり鋼鉄の握力で肩を掴まれ、振り向かされた。父王直属のクラード親衛隊のひとりだった。「殿下、安全な場所に避難なさってくだい」男は強く言った。そのまま通り過ぎ、塵の雲に突っこんで見えにくくなった。?ウンダヴァールは、その雲のなかに小さな人影を認めた。戦士の毒づきは、大声に変わった。「一歩でも近づいてみろ」?そう言いながら、剣を抜き放った。その刃が人影に振り下ろされると、ウンダヴァールの内側に興奮が戻ってきた。だが最後の瞬間、人影は杖のようなものを振り上げ、その打撃を弾いた。目の前で戦士は剣を落とし、両腕を背後にまわして身をかがめた。ありえない? 塵の中で何が起きているのか、よくは見えなかった。すると塵は変容した。暗黒の濃霧となり、拡大し、戦士の肉体を包みこんで引き裂いた。漆黒の取り縄のように締めあげられたクラード戦士の断末魔。枝を折るようなボキリという音と共に、そのまま崩れ落ちた。 死体を放り出した霧は、小柄な人影に吸いこまれていく。マントとフードに身を包んだその男は、ゆるりと近づいてくる。戦うことも、叫ぶことも、逃げ出すこともできないウンダヴァールは、ただ両目を見開くしかなかった。 「さてと、我が友よ」異邦人はそうささやき、ウンダヴァールに肉薄した。「いまお前が体験しているものこそが、恐怖と呼ばれる感情だ。どうやらあまりにも永き間、怖れを憶えずに過ごしてきたらしい。私は、その状況を変えることになる」 ウンダヴァールは、どもりながら何か言った。自分でも何を言ったのかわからない。 「お前の主の元へと連れて行け。奴隷どもの王の前に。なあに、贈り物があるのだ」 そこから何がどうなったのか、よく思い出せない。おそらく自分自身で、父王ゴンハールの玉座の間へと、その異邦人を案内したのだろう。剣や槍を手にした百体以上の骸骨剣士が、自分と灰色マントの男を半円状に遠巻きに囲んでいるのに気づき、我に返った。そこには親族もいた。妹エンネヴァール、皆から“鞭”と呼ばれる呪術師コリオン、死者の主トゥアヴァール将軍、そしてもうひとりの呪術師クホル。 広間そのものが緊張で震えているようだ。徐々に意識がはっきりしてきたウンダヴァールは、頭を振り、クラードの仲間たちの列に紛れた。異邦人と対峙するゴンハールが、上体を前後に揺らすさまを、みな不安げに眺めている。ゴンハールはクラードとしても極めて長身だ。その玉座は巨大な灰色の石で、ゴンハールを含む代々の父祖が座ることによって磨きあげられている。 「さあ、余所者よ。最後に自身にかけてやる言葉はあるか?」ゴンハールの声が響いた。「おまえを引っ掴み、炎によってゆっくりと死に至らしめる前に、わしに何を伝えたいのだ?」 異邦人は、末期の言葉を探しているかのように沈黙していた。代わりにウンダヴァールの口が、勝手に言葉をつむいだ。「この者こそが贈り物なのです、陛下」何てことだ! こんなことを言いたいわけもなかった。いったいどんな術をかけられたというのか? ゴンハールが片眉を上げると、異邦人が口を開いた。ささやきとたいして変わりがないにも関わらず、ウンダヴァールの耳には極めて明瞭に届いた。 「あなたが何者なのか知っています。ああ、あなたの素性をね、ゴンハール。遥か北に一本の樹がありまして、そこには人間が記録した歴史書が納められています。あまたの出来事が、知識が、伝説が書き留められていました。あなたのことも記録されていたのです。もろい羊皮紙の巻物の、効果も疑わしき森のキノコや薬草の解説のすぐわきに。私は、かの樹木の下で、長きにわたって明かされざる秘密について学びました。埃まみれの書棚に収められた、革装の書物のページをめくりながら、あなたの痕跡を探したのです。そしてついに見つけました」男はゆっくり顔を上げた。よく見ようと、ウンダヴァールは首を傾げた。フードの下に何とか見て取れたのは、濃い黒ひげを生やしたトカゲのような顔だった。「とても美しき装丁のなかに、あなたの最悪の所業を見つけ出したのです。いや、恐縮する必要はありません。悪しき行いこそ讃えられるべきもの!」男の顔は微笑みで歪んだ。「我が名はファルクル。そして実際に、贈り物を用意してきました。アンドールという名の贈り物を」 ゴンハールは人払いを命じた。例外は王子であるウンダヴァールのみ。その場には、彼と異邦人だけが残された。 男は続けて、アンドールの地と、かつてゴンハールの奴隷であった住人について語った。今その国を統治する王の名はソラルド。だが偉大なる父王ブランドゥルに比べれば、不肖の影に過ぎない。そしてまた邪魔立てする勇者たちと盾ドワーフのことも。ドワーフについては、その“洞窟”に配下の怪物を送りこんで弱体化させた。それによって、自分は気づかれずにここへ来ることもできた。 そのようにファルクルが語り終えると、しばし沈黙が辺りを支配した。ウンダヴァールですら、父王の反応は予想もつかなかった。 「おまえが言うところのアンドールの地は、常に一頭の竜の棲み処であった」王は、何とか言葉をつむぎだした。 「大王よ、そいつはさっき話した勇者どもによって片付けられてしまったのです」ファルクルが返した。 「竜を屠れるほどの勇者がおる場所に、わしらは行くべきだと? それほど強力な輩がおるのであれば、なにゆえに?」 「ああ、父上は罠にかけられてしまった」ウンダヴァールは思った。「この臆病者は、なんと巧緻に長けたことか」 「理由は2つ。そして最初の理由こそが、遥かに大事なものです。かの地の正当なる主は、あなたなのですからね、陛下」ファルクルは厳かにそう告げ、ウンダヴァールに振り返った。「そしてあなたの息子たちは、その高貴なる特徴を受け継いでいるようです。見間違えでなければ、わたしはこんな顔を見たことがあります。確かにクラードの巨人であり、勇敢な戦士でした」 「いったい誰のことを?」ウンダヴァールは訊いた。 「汝の父の次男、すなわち汝の弟。その名は確か、フェルンタールとか言いましたかな?」 フェルンタール。ウンダヴァールの弟であり、数年前から消息が知れなかった。ウンダヴァールと同じく心の虚無に蝕まれ、次男であるがゆえにいつか王位を継ぐという希望も抱いていなかった。あるとき焦燥感にかられたのか、フェルンタールは灰色山脈へと探索の旅に出てしまった。新たな奴隷か宝を見つけて来る。そう言い残して。 「フェルンタールについて、何を知っているのです?」ウンダヴァールは声を荒げた。 「ああ、よくない知らせをもたらすのは胸もつぶれる思いですな。アンドールの勇者たちに弑されたのは、何も竜のみに限らないのです。〈星の盾〉の時代にも、私はきゃつらと戦うことになりました。フェルンタールがかの地に足を踏み入れて間もなく、きゃつらに誘い出され、罠にかけられたのです」 ウンダヴァールは絶叫し、近くのテーブルに拳を叩きつけた。それは大広間の向こうまで、数ヤードも吹き飛んだ。すぐさま何人かのクラードの戦士と、五十を超す骸骨剣士が駆けこんできた。しかしゴンハールが目で制したため、再び静寂が訪れた。そして王はファルクルに向き直った。 「なるほど、魔道士よ。わしの興味を惹くことには成功したようだな。だが憶えておけ。わしは決して、おまえの計画のコマなどにはならぬ。贈り物とか言ったようだが、毒が塗られているな? 魔術師、盾ドワーフ、戦士、そして射手か。息子フェルンタールは罠にはまったようだが、わしは同じ過ちはおかさぬ。して、わしがわざわざ身の危険をおかして部下の下を離れねばならぬ、ふたつめの理由とは?」 「話しますとも。戻りましたら、私めは勇者どもを誘い出し、かの地を無防備にしてご覧にいれます。私自身を餌に、遥か北方へと連れ出し、死を与えるのです」 ゴンハールは両目を細めた。「失敗したら? おまえを倒して戻ってきたとしたら?」 「ありえませんな。万が一にもそうならないように、私はここを訪れたのですから……」ファルクルは決然と言い放った。「故国を離れ、ご自身の奴隷を取り戻しなさい。地下城屈と鉱山を、新たな血で満たすのです! アンドールこそ滅ぶべし! そして今度こそ屈辱を晴らさん!」 ファルクルの声が大広間に響き渡るなか、ゴンハールは眉をひそめた。 翌日ファルクルがボルクホルン要塞から出立する際、大門まではウンダヴァール王子が付き添った。 「父君は臆病で愚かな老人だな!」ファルクルは毒づいた。「私の贈り物を受け取るべきかどうか、まだ結論を下せずにいる。だが親愛なる王子よ、おまえは違う。王の怠惰と臆病のせいで、おまえの襲撃が止められてはならない。勇敢な弟を思い出すのだ。復讐を果たし、自分のものとなるべきだったものを取り戻すのだ」 ウンダヴァールは、ゆっくりと肯いた。 「それからもうひとつ」ファルクルは歩きながら言った。「もし私が遥かなる北方で敗れ、勇者たちが戻って来たときのために、警告しておこう。連中のなかで真に恐れるべきは唯ひとり。この手であの女を、苦痛に満ちた死へと追いやろうぞ。もしそれがならぬのなら、そいつを手にかけるのはおまえの役目だ。その名はチャダ。決して見くびってはならない。さあ、おまえの意志で山々を引き裂いてやれ」? クラードの地を離れたファルクルは、進路を北にとった。その物語は『北方への旅立ち』で語られている。 ウンダヴァールは夕空を眺めていた。曇っていて薄暗く、鉛のように灰色だ。虚無感は残っていたが、確かに大いなる興奮もあった。父王の許可があろうがなかろうが、みずから軍を組織し、何百という骸骨剣士を引き連れて、灰色山脈を超えるのだ。この地を離れ、魔道士の贈り物を手にするのだ。 兄弟の秘密
小屋の間近で、小声で話すふたりの背の高い男のくるぶしを、潮が浸していた。ひとりはかなり濡れており、冷たい北風のせいで身を震わせている。 「コグ船は沈んだ。たくさんの仲間が死んだ。人間どもには新しき指導者が立った。我らを追い立てた連中のひとりだ」 「落ち着いて、兄さん。一緒に私の小屋に行こう。そこで温まろう」 茶色の長いマントのもうひとりが、そう返した。月のない夜の闇のなか、兄弟ともにその肌が青白く光った。 「いいや。俺はもう行く。力を集めなくては。俺は、俺は……」そう言って、草や枝で葺かれた兄の小屋の屋根を見つめた。「お前のために、あの男を救ったのだ。使命を果たすために手を貸してくれるだろう」 「使命を果たす? あの男は今夜が峠なのに? 傷を手当してやらなければ、手を貸してくれるどころじゃないだろう?」 「言葉遊びはやめるんだ、レアンダー!」雫を滴らせながら叫んだ。「お前には予言の才があるだろう? あいつが生き延びれるかどうか、わかりそうなものじゃないか」 レアンダーは首を傾げた。弟ではあったが、常に兄より賢く忍耐強かった。兄は、早くに家を飛び出した。野心や活気に満ち溢れ、名誉欲の権化だった。そしてそれに値する存在なのだ……悪名ではあったが。一方、レアンダーは家に留まった。書に親しみ、なにがしかの癒しの術を習得した。それから言語への興味が膨れあがった。まず周囲の国々の言葉を学んだ。そしてある日、最も難しい言語まで習得した。“未来”である。それは一種の黒魔術で、まだ到来せぬ来たるべき出来事を見通すのである。もちろん黒魔術は常に代償を伴う。レアンダーの能力が増すにつれ、視力は徐々に衰えていき、ついには光を失った。遥か彼方を見通すことができる彼であったが、目の前にいる兄の存在は、その声でしか認識できないのだ。したがってキャレムがどれだけ堕落しているのか知ったのなら、また別のニュアンスで答えたのかもしれない。だが彼は叫んでいた。「簡単に言うなよ、この愚か者! 現在の影を突き抜け、未来の光を見て解釈するのは、たいへんなことなんだ」 キャレムは弟の両肩をきつく掴んだ。「あいつは獣だ。わからないのか? 皮を取り換える者だぞ! アンドールの勇者たちに破滅をもたらすことだろう。お前の助けがあればな、弟よ! やつらの城か宿営地かどこで、安心しきったすきを見計らって滅ぼしてしまうのだ!」 キャレムの声は浜辺を超えて海の彼方にまで響き、レアンダーは静かにするようにと制した。 「もう充分。アンドールの勇者たちへの恨みはよくわかったよ。兄さんの仇なら、ぼくの仇だ。兄さんの計画を、うまくいくようにやってみるよ……」 そんなセリフのさなか、彼自身の闇の中に小さな裂け目が広がり、近未来より到来する光で目がくらんだ。啓示だ! 予言者の双眸は、かつての輝きを取り戻したかのごとく、接近する人影のパターンを捕らえた。 「すぐにここを離れて。神意は我らとともにあり。狼が、忌々しき王の狼がやってくる。それと、もう1体の奇妙な生き物が。狼は兄さんの仲間を探してる。それに自分たちの仲間になりそうな相手も。それが極めて明瞭に見える……だからすぐにここを離れて、兄さん。心配しなくても、言われたことを実行に移すよ。何の疑いも持たない羊の群れにあの獣を放ち、兄さんの復讐を果たすよう仕向けるよ」 「わかった。よくやった、弟よ」キャレムは興奮し、息を荒げた。「あの女に同行し、友達になれ。そしていざというときに手のひらを返すのだ。そしてそれを仕組んだのがキャレムであることを知らしめよ。やつらが滅ぼしたと思ったこの俺が、やつらの運命を閉ざしたのだと」 キャレムはその場を去った。残された弟は、ドルキルという名の皮を取り換える者の傷を手当てし始めた。 朝の灰色の曙光のなか、森の縁の木々は、監獄の鉄格子のように黒いシルエットとなった。狼のローナスとハーフスクラルのフォルンは、そこを抜けて来た。 狼が先行した。自分が何を探しているのか、充分自覚していた。チャダから、さらなる勇者を見つけてくるようにと言いつかっていたからだ。狼に遅れをとることのないハーフスクラルのフォルンは、既にアンドール義勇軍への参加を決意していた。死霊術師のダールも同様だった。そしてついに、森の外れの小屋が視界に入ってきた。 物語は続く。果たしてドルキルが新たな仲間たちに破滅をもたらすのかどうかは、『アンドールの伝説:闇よりの勇者たち』を投入した伝説をプレイしてみて初めてわかるのだ! 大いに楽しんで! トゥルゴールの民
多くのトゥルゴールの民が、何年も何年も、かの山脈を抜ける道を探すべく挑んできた。生きて帰って来た者はいない。春の陽光が射し、雪解け水が険しい斜面を流れると、死体となって戻ってくる。古き言い伝えによれば、そこは精霊や魔神の棲み処なのだ。ザロは言い伝えを真に受けるほど信心深くはなかったが、山で長子を失うことを思うと気が気ではなかった。 「山を越えるわけじゃない」エフォラスが答えた。「ハアムンは、山中を抜ける道を知ってる……」 「あの山脈に抜け道などない!」 「かつてはね、父さん!でも俺たちトゥルゴールの民は、悠久の昔からメラ石を採掘すべく、ずっと岩盤に隧道を掘ってきた。そこを進むんだ」 ふたりの男は、しばし押し黙った。既に言うべきことは、全て話したと言わんがばかりに。やがてエフォラスは踵を返し、農家である小さな家を離れた。 ザロは無言のまま、息子が通り抜けた扉を眺めていた。 漆黒の夜は、灰色の朝に道を明け渡した。淡い霧のベールがトゥルゴールの地を包んでいる。肌寒い。ハアムンは自分の小屋の前に立ち、広大な地を眺め渡した。 ファーレ山脈を越えて、もう7~8年になる。トゥルゴールの民がクオレマと呼ぶあの山脈は、常に雲に包まれて実際の高さを推し量ることができない。だがハアムンは知っていた。かつては山頂に立ち、精霊や魔神の真実も目の当たりにしたのだから…… トゥルゴールの民は自分を温かく受け容れ、ハアムンと呼んだ。「曙光」という意味だそうだ。自分の体験談を信じる者は少なかったが、それでもここが第二の故郷となった。 当初は目的もなく、この未知の大地を、ただぶらぶらしていた。クオレマの麓に広がる、黄金なす広大なトウモロコシ畑。あちこちに藁葺き屋根の家屋が見え、冬には黒い煙突から濃い煙がたなびく。土地は肥え、農民は忙しく立ち働いた。 遥か西を見やれば、荒れた平地である。無限に続くかに見える草原地帯だが、少人数の村が散らばり、みな羊と山羊に頼って暮らしている。 やがてハアムンは、商人の一団に加わった。北方に旅し、より大きな集落を抜け、比類なき家屋や橋や城を目にした。トゥルゴールの民は建築技術に秀でていたのだ。 晩秋、ハアムンは港もない険しい岸壁に到達し、ついに例の山脈まで戻ることにした。そこで鉱夫たちの手伝いをした。何世紀ものあいだ、金、銀、鉄、そして貴重なメラ石が採掘されていた。メラとは「赤き月の輝き」という意味で、年に数日だけ、山裾で輝きだす。トゥルゴールの民は、何世代も採掘の技術に磨きをかけてきた結果として、光を岩壁で反射させ、山のより深くへと到達させることができた。わずかだが、月の光に触れて自ら輝き出す岩が見つかる。そんなメラ石は、月が動いてしまう前に、すぐさま岩床から掘り出された。そうやって何年か過ごした。ハアムンは草原で、貴重な、あるいはまだ知られていない薬草を数多く集めた。水薬を醸造し、さまざまな軟膏、粉薬、毒のたぐいを調合した。それらをたずさえ、山の奥深くまで続く隧道を行くと、山脈の向こう側に戻る方法がないか、ついつい考えこんでしまう。 そしてこの結集の朝、ハアムンは自分の小屋の前に立ち、薄霧に包まれたクオレマを見上げていた。ほんの二日ほど前、一時的に雲が晴れ、雪に覆われた峰々が姿を覗かせた。山脈の向こうの空が赤くい輝きに満ちたとき、ハアムンは老王が倒れ、竜もまた屠られたことを知った。帰郷すべき刻だ。 やがて幾筋かの曙光が、みなを照らした。ハアムン、エフォラス、そして山の精霊に対する恐怖より未知への好奇心が上回る十人余りのトゥルゴールの商人、大工、地図作成者。 山中の隧道に足を踏み入れ、深い闇に包まれたハアムンは、ひとりほくそ笑んだ。かつて怒りと共に去った地に、ついに戻るのだ。かの地では、もはやハアムンなどではない。人は彼を、アンドールよりの魔術師メラスと呼んだ。 氷の魔神ズィアンタリ |